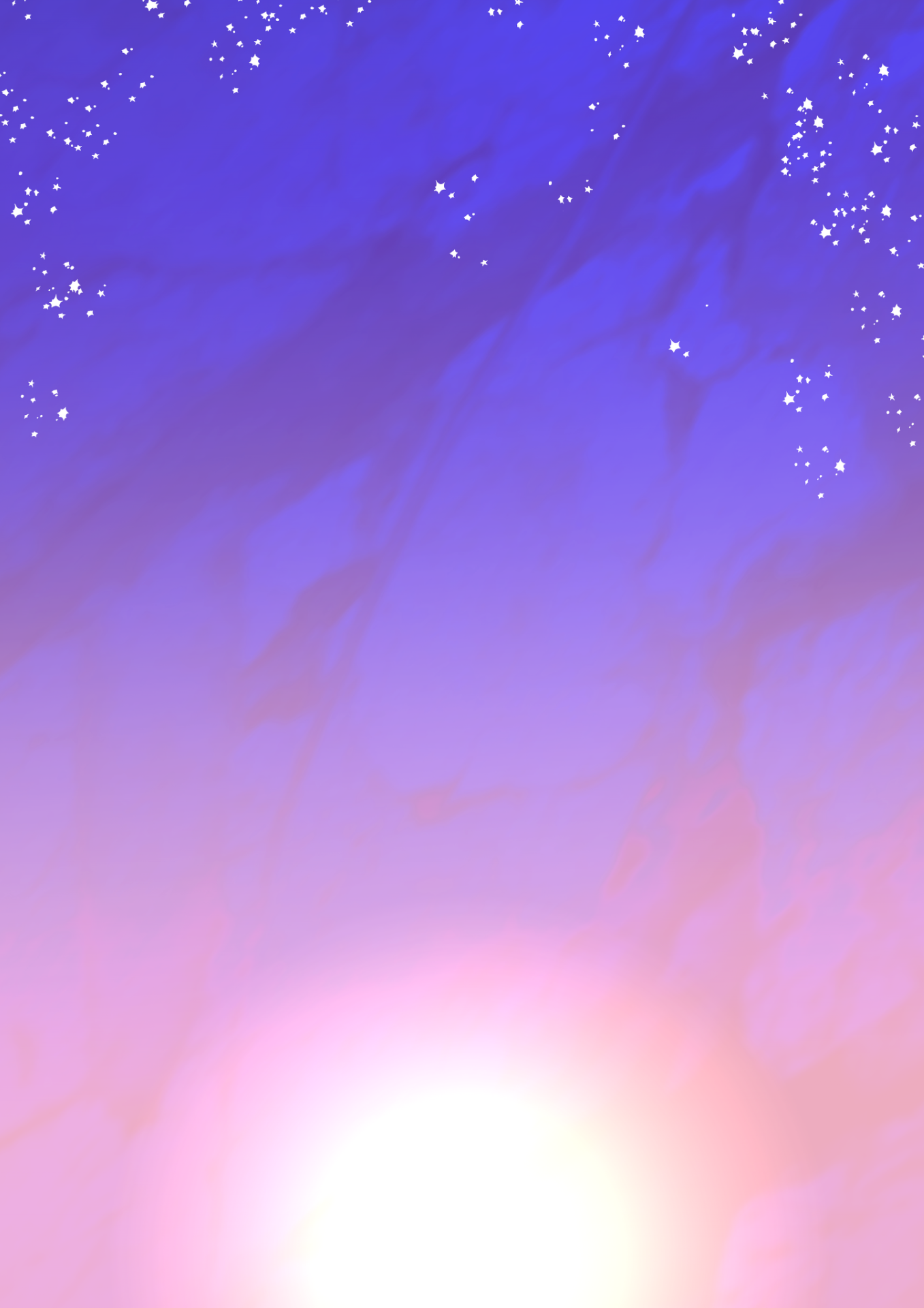ハラスメント防止ポリシー
だれもが安心して創作に携われるように
ハラスメント防止ポリシー
0. 文献等
- 立命館大学ならびに学校法人立命館の設置する小学校、中学校および高等学校ハラスメント防止に関する規程(規程第731号) 2007年6月20日
- 立命館大学・立命館付属校ハラスメント防止のためのガイドライン
1. 目的・定義
このガイドラインは、劇団創世風座(以下、当劇団)におけるハラスメントの防止のための措置およびハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることにより、当組における制作上の公正の確保ならびに制作クルー・キャストの利益の保護を図ることを目的とする。
本ガイドラインにおいて「ハラスメント」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に該当する行為をいう。
(1) 「セクシュアル・ハラスメント」
当組における各種の活動と関連して、性的な言動により、相手に対し、不利益な処遇を与え、またはその活動に係る環境を害する行為(適正な権限の行使にあたるものを除く。)
(2) 「パワー・ハラスメント」
制作活動と関連して、活動上の優位な立場にもとづく言動(性的な言動を除く。)により、相手に対し、当該活動上の関係において不利益な処遇を与え、またはその活動に係る環境を害する行為(活動上必要かつ相当な範囲内のものを除く。)
2. ハラスメントをしないための基本的な心構え
当劇団の制作に関係する者は何人も、自らのコミュニケーションにおいて基本的人権の尊重の観点を重視し、自身の行為がハラスメントとならないよう心がけなければならない。個人間のきわめて多様な価値観が、認識の齟齬を生みうることを認識し、表現には配慮しなければならない。また受け手が不快感を明示的または黙示的に、或いは形式的または実質的な形を以て示した場合、謝罪の上同じ言動を繰り返してはならない。
3. ハラスメント被害に対する対処
ハラスメントが行われたことについて、被害者にはいかなる責任も負うことはない。被害を受けた際には、行為者には自覚なき場合もある。敵対関係にない場合であれば、行為者の行為がハラスメントにあたり、自分がこれに不快感を抱いていることを、口頭または文書で直接伝えることができる。何人も行為者としてこれを伝えられた場合、これを即座に否定することはしてはならない。また、何らかの理由で加害者に直接伝えることができない場合は、所属する部署の長・座組の演出・劇団の主宰、副主宰等の要職者に状況を伝えることも、問題の解決については有効である。
このほか、身体に危険が及ぶ場合には、友人や劇団の他のメンバーに助けを求め、場合によれば警察へ連絡する。なお警察に行く場合には、劇団の主宰・副主宰等の要職者が同行することができる。